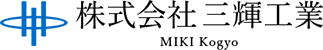NEWS最新情報
2025.11.02ブログ
大阪市の解体工事で共有ブロックでトラブルが起こらない為に

こんばんは!大阪の解体業者である株式会社三輝工業のブログ担当です!
「隣の家との共有ブロック塀をどうにかしたい」
「老朽化した境界線フェンスの解体で、隣人と揉めたくない」と、お悩みではありませんか?
ブロック塀の撤去やフェンスの解体は、お隣様との関係が絡むデリケートな問題です。
法律や費用分担が複雑で、「どこから手をつけていいかわからない」という不安や、
隣人様とトラブルになるケースが多くあります。
この記事では、共有ブロック塀の撤去や境界線フェンスの解体に必要な費用、法律、手順、
そして隣人トラブルを回避するための具体的な方法を、他のどのサイトよりも詳しく、分かりやすくご紹介します。
この記事を読むと、共有ブロック塀が誰のものなのか、撤去費用の正しい分担方法、
隣人との交渉をスムーズに進めるための具体的なステップがこの記事で分かります!
老朽化したブロック塀の撤去を検討している方、境界線フェンスの解体で隣人との関係に悩んでいる方、
大阪付近で解体工事を検討している方はぜひ最後まで読んでみてください!
共有ブロック塀の撤去・境界線フェンスの解体で知っておくべき基本
共有ブロック塀の撤去や境界線フェンスの解体を検討する際、まず知っておくべきは、
その所有権と解体工事の基本的な流れです。
この基本を押さえることが、後のトラブル回避につながります。
共有ブロック塀とは?単独所有との違いと確認方法
共有ブロック塀とは、隣接する 2 つの敷地の境界線上に設置され、
両方の所有者によって共有されているブロック塀を指します。
一方、単独所有のブロック塀は、境界線からどちらかの敷地側に完全に寄せて設置されているものです。
共有ブロック塀であるかどうかの確認方法は、主に以下の 3 点です。
| 境界線標(境界杭)の位置:ブロック塀の中央に境界線標がある場合は、共有ブロック塀である可能性が高いです。 |
| 設置費用の分担:過去に両家で費用を分担して設置した記録があれば共有物です。 |
| ブロック塀の見た目:ブロック塀の天端(一番上の面)が平らで、境界線に対してどちらかに大きく偏っていない場合も、共有ブロック塀の可能性があります。 |
単独所有のブロック塀であれば、基本的に所有者が単独で撤去や解体を決定できますが、
共有ブロック塀の場合は、必ず隣人との合意が必要になります。
境界線フェンスを解体する主な理由とメリット
境界線フェンスを解体する主な理由は、老朽化による危険性の排除、新しいフェンスへの交換、またはブロック塀の撤去に伴う全体の刷新です。
境界線フェンスを解体し、新しくすることで得られるメリットは以下の通りです。
- 安全性の向上:老朽化や地震などで倒壊の危険があるフェンスやブロック塀を撤去することで、人命に関わる事故のリスクをなくします。
- 見た目の改善:古くなったフェンスやブロック塀を一新し、家の外観と敷地全体の印象を向上させます。
- 境界の明確化:新しいブロック塀やフェンスを設置する際に、専門家による測量を行うことで、境界線を明確にでき、将来の隣人トラブルを未然に防ぎます。
撤去・解体工事の主な流れ(隣人への相談から完了まで)
共有ブロック塀の撤去や境界線フェンスの解体工事は、次の流れで進めるのが一般的です。
| 隣人への相談・合意形成:これが最も重要です。撤去・解体の理由、費用分担、工事期間などを書面で確認し、合意を得ます。 |
| 解体工事業者の選定と見積もり取得:複数の大阪府の複数業者から見積もりを取り、費用、工期、実績を比較します。 |
| 契約と工事準備:契約後、業者が近隣住民への挨拶や、必要に応じて役所への届出を行います。 |
| 撤去・解体工事の実施:ブロック塀やフェンスを丁寧に解体・撤去し、廃材を適切に処理します。 |
| 工事完了と確認:解体箇所を確認し、新設工事を行う場合はそのまま移行します。 |
共有ブロック塀の撤去・解体における法律と費用分担のルール
共有ブロック塀の撤去や解体を円滑に進めるためには、法律、
特に民法に基づいた費用分担のルールを理解することが不可欠です。
民法上の「共有物」とブロック塀の撤去・解体に関する規定
共有ブロック塀は、民法第 225 条に規定される境界標や囲障(いしょう:囲い)に準ずるものとして扱われることが多く、
原則として隣地所有者との共有物とみなされます。
民法上、共有物の変更(撤去・解体を含む)は、共有者全員の合意が必要です(民法第 251 条)。
つまり、共有ブロック塀を撤去・解体するには、必ず隣人の同意を得なければなりません。
また、境界線付近に設置されたブロック塀やフェンスは、民法第 225 条により、
境界線付近の囲いの設置義務が定められており、撤去後の対応についても話し合いが必要です。
撤去・解体費用の基本的な分担方法
共有ブロック塀の撤去・解体にかかる費用は、原則として共有者である隣人と折半となります。
ただし、ブロック塀の設置目的や費用分担の経緯、撤去に至った原因(例:一方の敷地側の老朽化が著しいなど)によっては、
折半以外の割合で費用を分担することもあります。重要なのは、法律の規定を前提としつつも、
最終的には隣人との話し合いで合意することです。
例えば、ブロック塀を撤去し、新たに一方の敷地に寄せてフェンスを設置する場合、
新しいフェンスの所有者が全額費用を負担することになるのが一般的です。
トラブルを防ぐための費用分担の取り決め方(書面化の重要性)
費用分担に関するトラブルを確実に避けるためには、隣人との合意内容を必ず書面に残すことが極めて重要です。
口頭の約束だけでは、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になりかねません。
作成する書面には、以下の項目を具体的に記載してください。
- 撤去・解体するブロック塀またはフェンスの場所と範囲
- 撤去・解体の費用総額と分担の割合
- 費用の支払期日と支払方法
- 解体後の境界の取り決め(フェンスなどを新設する場合)
- 工事期間中の連絡方法
この書面は、両者が署名・押印した上で、各自が保管するようにしましょう。
境界線フェンスの解体・ブロック塀の撤去に必要な手続き
境界線フェンスの解体やブロック塀の撤去は、隣人との関係をスムーズに進めるための手続きが特に重要になります。
隣人との話し合いで合意形成をするための具体的なステップ
共有物であるブロック塀の撤去は、隣人への配慮と具体的な根拠をもって交渉に臨むことが大切です。
- 現状の共有と問題提起:老朽化の状況を写真などで具体的に共有し、撤去・解体が安全上必要であることを客観的に伝えます。
- 複数の見積もりを提示:費用に関する透明性を示すため、大阪府で複数の解体業者から取得した見積もりを隣人に提示します。
- 代替案の提示:ブロック塀を撤去した後の境界について、フェンス設置などの代替案を提示し、隣人の意見を聞きながら合意点を探ります。
- 期限の設定:合意形成に長期間かかることを避けるため、「〇月〇日までに結論を出したい」と期限を設定します。
撤去・解体工事で発生する可能性のある損害賠償リスクとその対策
解体工事中に、振動や騒音、ブロック塀の破片などが原因で、隣人の家や植栽に損害を与えるリスクがゼロではありません。
このリスクに対する対策は、トラブル回避の鍵となります。
対策として、以下の 2 点が重要です。
- 業者の選定:解体工事の実績が豊富で、丁寧な作業を行う業者を選ぶことです。業者の担当者が隣人への配慮を怠らないかも確認しましょう。
- 保険の確認:解体業者が「請負業者賠償責任保険」に加入しているか必ず確認してください。万が一損害が発生した場合、保険で対応できる体制を整えておくことが重要です。
建て替えや新設で必要な建築基準法上の手続きと注意点
ブロック塀を撤去した後、新しいブロック塀を新設する場合、建築基準法や各自治体の条例を遵守する必要があります。
特に、ブロック塀の高さ、厚さ、控え壁の設置基準が厳格に定められています。
注意点として、高さ 2.2m を超えるブロック塀は建築確認申請が必要になることがあります。
また、地震による倒壊を防ぐため、控え壁や基礎の構造も重要です。これらの基準を満たすことは
安全かつ適法に工事を進める上で不可欠です。解体業者だけでなく、建築士や行政にも確認を取りましょう。
ブロック塀の撤去・境界線フェンスの解体にかかる費用の相場
共有ブロック塀の撤去や境界線フェンスの解体を進める上で、最も気になるのが費用です。
適切な相場を知っておくことで、解体業者からの見積もりが適正かどうかを判断できます。
ブロック塀の構造・長さ・厚さ別の撤去費用目安
ブロック塀の撤去費用は、主にブロックの種類、厚さ、高さ、長さによって大きく変動します。
| 構造 | 厚さ | 1 m あたりの撤去費用目安 | 備考 |
| コンクリートブロック塀 | 10cm〜15cm | 約5,000円〜10,000円 | 最も一般的なブロック塀の相場 |
| コンクリート擁壁 | 20cm以上 | 約15,000円〜30,000円 | 基礎工事が深く、撤去費用が高くなる |
| 生垣・その他の囲い | – | 約3,000円〜6,000円 | 根の撤去作業が別途発生する場合がある |
上記はあくまで目安であり、作業のしやすさ(重機が入るか)、廃材処理費の高騰などにより費用は変動します。
業者から現地調査に基づく正確な見積もりを取得することが重要です。
フェンスの種類(メッシュ、アルミなど)別の解体費用と注意点
境界線フェンスの解体費用は、ブロック塀よりも比較的安価になる傾向があります。
| フェンスの種類 | 1 m あたりの解体費用目安 | 備考 |
| メッシュフェンス | 約2,000円〜4,000円 | 比較的簡単に解体でき、費用が安い |
| アルミフェンス | 約3,000円〜6,000円 | 支柱の基礎解体費用が別途かかる場合がある |
| 木製フェンス | 約2,000円〜4,000円 | 廃材処理費用が変動する場合がある |
解体の注意点として、フェンスの支柱がコンクリートで固められている場合、その基礎を撤去するための費用が別途発生します。
見積もりの際には、「基礎解体が含まれているか」を確認しましょう。
費用を抑えるためのポイントと補助金制度の活用
ブロック塀の撤去・解体費用は、工夫次第で抑えることが可能です。
- 複数の業者から見積もり:複数の解体業者から相見積もりを取り、費用とサービスを比較します。
- 撤去範囲の最小化:老朽化が激しい部分のみなど、必要最小限の範囲に撤去を留めることも費用削減につながります。
- 自治体の補助金制度:地震による倒壊の危険性があるブロック塀の撤去に対して、各自治体が補助金制度を設けている場合があります。
共有ブロック塀の撤去・解体でよくあるトラブル事例と解決策
共有ブロック塀の撤去・解体は隣人が絡むため、トラブルになるリスクを常に伴います。
しかし、事例と解決策を知っておけば、トラブルを回避したり早期解決したりすることが可能です。
隣人が撤去・解体に同意してくれない場合の対処法
隣人が「費用を払いたくない」「ブロック塀を撤去する必要がない」といった理由で同意してくれない事例は少なくありません。
解決策として、以下のステップを踏んでください。
- 危険性の客観的な提示:ブロック塀の傾きやひび割れの状況を、建築士や専門家に診断してもらい、「危険性がある」という客観的な意見を提示します。危険を共有することで、隣人の意識を変えることが重要です。
- 費用の譲歩:費用に関する対立であれば、「費用の一部を多く負担する」など、隣人の負担を軽減する譲歩案を提示することも解決につながります。
- 法律の専門家に相談:話し合いで合意に至らない場合は、弁護士などの専門家に相談し、裁判や調停といった法的手続きの可能性も検討します。
費用負担について意見が対立した場合の解決方法
「費用の折半に納得できない」と隣人が主張する場合の解決方法です。
解決策は、第三者の介入を検討することです。具体的には、
「境界に関する専門家である土地家屋調査士」や「弁護士」を交えて話し合いを行う方法があります。
第三者が法律に基づいた意見を示すことで、感情的な対立から合理的な解決へと移行しやすくなります。
また、話し合いを公開の場で行う「ADR(裁判外紛争解決手続き)」や「調停」といった公的な機関の利用も有効な手段です。
境界線が不明確な場合の確認方法(筆界特定制度など)
ブロック塀やフェンスを撤去・解体する際に、境界線が不明確になる事例もあります。
境界が曖昧なまま工事を進めると、隣人との新たなトラブルの原因になりかねません。
解決策として、土地家屋調査士に依頼し、境界を確定させる「境界確定測量」を行うことが最善です。
この測量に基づき、境界線に境界杭やプレートを設置することで、将来にわたって境界が明確になります。
隣人が境界の確認に応じない場合は、法務局が主体となって境界を特定する「筆界特定制度」を利用することも可能です。
ブロック塀の撤去後の選択肢:新しいフェンスまたはブロック塀の設置
ブロック塀を撤去した後の境界について、新しい囲いを設置するかどうかは、隣人との合意が重要です。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、最適な選択肢を選びましょう。
新しい境界線フェンスのメリット・デメリット
新しいフェンスは、ブロック塀よりも安価で工期も短いことが一般的です。
| 項目 | メリット(利点) | デメリット(欠点) |
| メリット | 通風・採光が確保できるため、圧迫感が少ない。費用が安く、工期が短いため、手軽に設置できる。デザインの種類が豊富。 | ブロック塀ほどの耐久性や目隠し効果は期待できない。高さに制限がある場合がある。 |
フェンスは目隠しを目的とするルーバータイプや、通風を優先するメッシュタイプなど種類が豊富です。
隣人のプライバシーや景観にも配慮したデザインを選ぶことが重要です。
新しいブロック塀を設置する際の注意点と選び方
新しいブロック塀を設置する際は、耐久性や強度を重視する必要があります。
注意点として、建築基準法に適合した構造にしなければなりません。特に、高さ、鉄筋の配置、基礎の深さなどを守ることが重要です。
ブロック塀の選び方としては、化粧ブロック(デザイン性のあるブロック)や
軽量ブロックなどがあり、費用や見た目を考慮して選びます。
ブロック塀は一度設置すると撤去が大変なため、信頼できる業者に依頼し、長期にわたって安全な構造を確保しましょう。
境界を明確にするための測量・杭打ちの重要性
ブロック塀を撤去した後、新しい囲いを設置する前には、必ず「境界確定測量」を実施し、境界杭を設置することが重要です。
境界杭は、隣人との敷地の境を未来永劫にわたって明確にする唯一の手段です。
隣人の同意を得て測量を行うことで、将来の不動産の売買や相続の際にもトラブルを防ぐことができます。
測量の費用は発生しますが、安心を買うための必要経費と考えてください。
境界線フェンス解体・ブロック塀撤去で安心できる業者の選び方
ブロック塀の撤去やフェンスの解体は、近隣トラブルに発展する可能性があるため、業者の選び方が極めて重要です。
安心して任せられる業者を選ぶためのポイントをご紹介します。
解体工事業者の選び方で失敗しない 4 つのチェックポイント
信頼できる解体業者を選ぶには、次の 4 つの点を必ず確認してください。
- 解体業の許可:「建設業許可」または「解体工事業登録」を取得しているか確認します。無許可の業者は避けるべきです。
- 賠償責任保険:工事中の事故や隣人への損害に対応できる「請負業者賠償責任保険」に加入しているか確認します。
- 見積もりの明瞭さ:「本体工事費」、「廃材処分費」、「重機使用料」などが明確に記載されているか確認します。一式表記の見積もりは要注意です。
- 近隣への配慮:隣人への挨拶や説明を丁寧に行ってくれる姿勢があるか確認します。
安心できる実績がある業者の見分け方
実績を見分けるためには、業者のホームページで過去の解体工事の事例やお客様の声を確認しましょう。
ブロック塀やフェンスの解体を専門とする事例が多い業者であれば安心です。また、地元での評判を聞くことも有効です。
見積書を徹底比較する際の注意点(追加費用の有無など)
相見積もりを比較する際、最も注意すべきなのは「追加費用」の有無です。一見、安く見える見積もりでも
後から追加費用を請求されるケースがあります。
内訳を確認し、「アスベストの有無」、「地中埋設物の有無」、「残土処理費用」
などが明記されているかチェックしてください。
業者に対し、「見積もりに含まれない作業が発生した場合の対応」を書面で確認しておくと安心です。
境界線フェンス解体・ブロック塀撤去に関するよくある質問
撤去工事期間中の騒音や振動対策は?
ブロック塀やフェンスの解体には、重機によるハツリ(破壊)作業が伴うため、騒音や振動は避けられません。
対策として、業者は工事開始前に隣人へ挨拶と工事期間の説明を行い、理解を求めることが義務付けられています。
作業時間を限定し(例:午前 9 時〜午後 5 時)、防音シートを設置するなどの対策も行います。
業者が隣人への説明を代行してくれるか?
基本的に、隣人との合意形成は施主様ご自身で行うのが原則です。しかし、優良な解体業者は、
隣人への工事内容やスケジュールの説明、挨拶回りなどを代行してくれる場合がほとんどです。
費用や法律に関する技術的な質問には、業者が専門家として対応することで、施主様の負担を大幅に軽減できます。
撤去後に新しくフェンスを作る場合の費用分担は?
共有ブロック塀を撤去した後、新しくフェンスを設置する場合、費用分担は設置の方法によって異なります。
- 境界線上に設置:共有物となるため、費用は隣人と折半が原則です。
- 一方の敷地内に設置:単独の所有物となるため、設置した側が全額負担するのが一般的です。
設置前に、どちらの方法で行うか明確にし、費用の取り決めを書面で交わすことが重要です。
まとめ:共有ブロックでもめない為に!
知識がない業者に頼んで、解体中、解体後にトラブルになる事はざらに
ある事で、せっかく工事が始まって、業者選びも終わってほっと一息ついて
後は工事が終わるだけだと思っていたのに、矢先にトラブルになってしまう事が多くあります。
そうはならないように、業者選びの時点でただ単に安いだけを求めてしまうと
結果的によくはなりません。
ですので、今回の記事の中で最も重要なポイントで、
1.知識がある業者を選定する
2.後々のトラブルを避ける為に業者選びから慎重になる
この2つを知っておく事で解体工事をする上で損が生まれないようにできますので
是非、参考にしてみてください!